【最新版】令和7年税制改正 個人所得税のポイントについて徹底解説!
◆はじめに
令和7年度税制改正では、物価上昇や賃上げの流れを踏まえ、個人所得課税の見直しが注目されています。
政府の方針として「働く世代の可処分所得を拡大し、消費を下支えする」ことが掲げられ、所得税・住民税双方にわたる調整が行われました。
今回は個人所得税の改正内容にスポットを当てて解説していきます。
◆定額減税について
令和6年分で導入された定額減税の一時的な措置が、令和7年度からは制度的に整理され、給与所得者や年金受給者にも分かりやすい形で運用されます。
具体的には、所得税で1人当たり3万円、住民税で1万円の減税が維持される一方、今後は物価・所得動向に応じて見直す仕組みが設けられました。
これにより、賃上げ効果を相殺しない形で可処分所得を確保する狙いがあります。
◆給与所得控除や基礎控除の見直しについて
給与所得控除や基礎控除の見直しについても議論が進みました。
高所得者に偏る減税効果を是正するため、基礎控除の一律拡大ではなく、中間層を中心に負担軽減を図る方向性が示されています。
特に年収850万円超の層に対しては、引き続き「所得制限付き控除」の見直しが検討されています。
◆事業所得の明確化
副業やフリーランスの増加を受け、所得区分の適正化が進められます。
従来、雑所得として扱われていた一部の副業収入について、事業所得として認められる範囲を明確化し、青色申告の対象拡大を図る方針です。
これにより、クラウドワークやデジタルコンテンツ収入などの新しい働き方にも税務上の公平性が確保されます。
◆金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化も重要な論点です。
上場株式等の譲渡所得・配当所得に対する20.315%の税率を維持しつつ、少額投資非課税制度(NISA)の恒久化後の利用状況を踏まえ、長期保有優遇やリスク分散投資へのインセンティブを強化する方向で制度調整が進められます。
◆住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除について、金利上昇を背景に適用期間や控除率の見直しが焦点です。
令和7年入居分からは、環境性能の高い住宅への優遇をさらに拡充し、一般住宅との差を拡大することで、脱炭素社会への移行を後押しします。
◆まとめ
総じて令和7年における税制改正は、「賃上げ」「物価高」「新しい働き方」という3つの課題に対応する構成になります。
実務では、年末調整や確定申告における控除適用の確認がこれまで以上に重要となるため、早めの情報整理が求められます。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊所へご相談下さい。

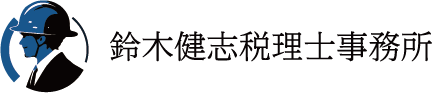 副業20万円ルールの正しい理解と実務対応
副業20万円ルールの正しい理解と実務対応