法人設立日を工夫して5,900円節税?法人住民税均等割の仕組みを解説
◆はじめに
会社を設立すると、たとえ赤字であっても毎年「法人住民税均等割」という税金を支払う必要があります。
均等割は、事業の利益や売上に関係なく「会社を設立したこと」自体に対して課される税金です。
この均等割について、法人の設立日を少し工夫するだけで、最大5,900円程度の節税ができるケースがあります。
今回は、その理由と実際の注意点について税理士の視点からわかりやすく解説します。
◆法人住民税均等割とは
法人住民税は、法人税割と均等割の2つから構成されています。
このうち「均等割」は、利益が出ていなくても毎年必ず課税される税金です。
都道府県民税と市町村民税の両方に含まれており、主に資本金額と従業員数によって税額が決まります。
たとえば、資本金1,000万円以下・従業員数50人以下の小規模法人であれば、
・都道府県民税:2万円
・市町村民税:5万円
合計7万円が毎年の最低課税額となります。
赤字でもこの税金は発生するため、事業を始めたばかりの会社にとっては、負担の大きい固定費となります。
◆設立日で税額が変わる仕組み
均等割は「事業年度の月数」に応じて月割計算されます。
1年(12ヶ月)に満たない事業年度の場合、12で割って月数分の均等割が課税されます。
例えば、
・事業年度:4月1日~翌年3月31日
・設立日:3月25日
上記の場合、初年度は3月25日〜3月31日の7日間だけの事業年度となります。
この場合、「1ヶ月分」として均等割が課税されます。
一方、もし設立日を1週間早めて3月20日にしてしまうと、「3月20日〜3月31日」の12日間でも同じく1ヶ月とカウントされます。
税額は変わらないため、この場合には節税効果はありません。
しかし、翌年度の開始日を意識せずに4月1日設立としてしまうと、4月1日~翌年3月31日の「12ヶ月丸々」課税対象になります。
つまり、3月末に設立して「数日間だけの初年度」をつくることで、初年度分の均等割を7万円 → 約5,900円節約できるのです。
◆設立日の決め方と注意点
節税のために3月末設立を狙う場合、以下の点に注意が必要です。
①定款認証・登記のスケジュール
法務局の登記日が「設立日」となるため、登記書類の提出日や混雑状況を考慮する必要があります。
年度末は申請が集中するため、余裕をもって準備しましょう。
②会計期間の設定
短い初年度を設けた場合、すぐに決算・申告の手続きを行う必要があります。
決算・申告の手間を考えると、節税額よりも事務負担が上回ることもあります。
③節税効果の限界
均等割は最大でも5,900円程度しか軽減されません。
設立日をずらす目的が節税だけの場合は、トータルのコストや労力を踏まえて慎重に判断すべきです。
◆まとめ
法人住民税均等割は、利益の有無にかかわらず課される固定的な税金です。
ただし、設立日を◯月2日〜31日(1月未満)に設定することで、初年度分を月割計算することができ、5,900円の節税が可能です。
もっとも、この節税効果は限定的であり、登記の手続きや決算スケジュールへの影響も無視できません。
節税を目的に設立日を調整する場合は、税理士など専門家に相談のうえ、資金繰りや会計処理の実務負担まで考慮して決定することが望ましいでしょう。
ご不明な点がございましたら是非弊所へご相談下さい。

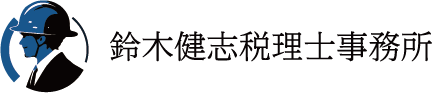 少額減価償却資産の特例改正のポイントと活用方法
少額減価償却資産の特例改正のポイントと活用方法