賃上げ促進税制について
賃上げ促進税制とは、企業の賃上げを促進するための制度です。
今回はこの賃上げ促進税制について、制度の概要、適用要件や注意点について解説したいと思います。
前提として、青色申告をしている事業者であればすべての企業が対象となります。
対象となる企業は、大企業、中堅企業、中小企業(個人事業主含む)と3つに区分されていますが、本記事では中小企業(個人事業主含む)を前提に解説していきます。
◆賃上げ促進税制の概要
賃上げ促進税制とは、対象となる企業や個人事業主において、従業員等に対する給与支給額が前年に比べて一定以上増加している場合、その増加額に応じて法人税額から税額控除する事ができる税制上の優遇措置になります。
なお、税額控除の上限額は、法人税額または所得税額の20%までとなっています。
令和6年度税制改正において、物価上昇を超える持続的な賃上げを目指す観点から、3年間の延長・拡充が行われています。
◆賃上げ促進税制の適用要件
①対象企業
賃上げ促進税制が適用できる企業は、青色申告を提出する事業者全てが対象となっています。
具体的には事業者を、大企業向け、中堅企業向け、中小企業(個人事業主含む)向けにそれぞれ内容が規定されています。
本記事では、中小企業を前提に解説します。
対象となる中小企業の定義は以下の通りです。
中小企業:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主
賃上げ促進税制の適用が出来る条件として、「必須要件」と「上乗せ要件」があります。
必須要件とは、従業員に対する給与が前年に比べて一定割合以上増加していることが要件となります。
必須要件を満たす事で、上乗せ要件の適用有無を検討します。
② 適用期間
2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業主の場合、2024年から2027年までの各年が対象)
③必須要件と上乗せ要件
必須要件は、中小企業の場合、下記要件を満たしている必要があります。
・継続雇用者に対する給与等支給額の増加率が前年度比で1.5%〜2.5%以上
給与とは、毎月の給与や賞与、残業手当、休日出勤手当などが該当します。
なお、退職金といった、通常給与に該当しないものについては給与とはみなされないので、賃上げ促進税制の判定に退職金は考慮外です。
賃上げ促進税制は、税額控除率の上乗せ要件として、1つ目として教育訓練費が挙げられます。
国内雇用者に対する教育訓練費が前事業年度と比べて5%以上増加しており、かつ、教育訓練費の金額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合には、中小企業であれば10%控除率が上乗せされます。
税額控除率の上乗せ要件の2つ目として、くるみん認定・えるぼし認定による税額控除率の上乗せが挙げられます。
これは2024年改正で出来たもので、子育てとの両立や女性が活躍する為の支援として受けられる制度になります。
具体的には、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「くるみん」認定、または「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「えるぼし」認定を取得している事が要件として挙げられます。
中小企業の場合には、5%控除率が上乗せされます。
◆注意点について
賃上げ促進税制を適用する上で、事前の手続きは必要ありません。
法人の場合、決算時に下記資料を添付すれば賃上げ促進税制の適用を受ける事が出来ます。
・別表(法人税申告書)
・適用額明細書
・給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
また、令和6年度の税制改正において、中小企業に限り、控除を5年間繰越できるようになりました。
控除上限額は、法人税額または所得税額の20%までとされていますが、中小企業においては翌年度以降、5年間の繰越しが可能となった為、適用事業年度に赤字であったとしても翌年度以降に適用することができ、長期的な節税効果があります。
◆まとめ
賃上げ促進税制は、これまでは利益が出ている場合に検討が必要でしたが、令和6年度改正で赤字であっても繰越が可能となりました。
したがって、これまで同様に赤字であったとしても賃上げ促進税制について検討することをおすすめします。
何かご不明な点がございましたら是非弊所までご相談ください。

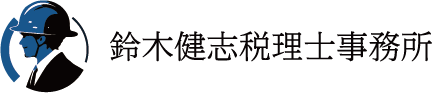 少額減価償却資産の特例改正のポイントと活用方法
少額減価償却資産の特例改正のポイントと活用方法