バーチャルオフィス利用時における納税地や税務調査の対応について
近年、リモートワークの普及により、オフィス環境を不要とする法人が増えています。
こういった場合、バーチャルオフィスを利用する法人が多くなっています。
バーチャルオフィスを利用した場合、さまざまなメリットがある一方で、税務調査時にはどのように対応すれば良いか悩む事業者も多いです。
今回はバーチャルオフィスの概要を解説することに加えて、税務調査時にはどのように対応すれば良いかを解説していきます。
◆バーチャルオフィスを利用している場合の納税地について
結論として、バーチャルオフィスを利用している法人の納税地は、本店所在地になります。
そもそも納税地とは、納税を行うにあたり、どこの管轄税務署へ確定申告書の提出と納税を行うべきなのかを判断するための重要な要素になります。
確定申告をする上で、納税地を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。
なお、納税地とは、国税である所得税や法人税、消費税を納めるために使用する用語になります。
注意すべき点として、法人事業税や住民税などの地方税は、納税地という用語は使用しません。
バーチャルオフィスとは、仮想のオフィスをレンタルすることが出来るサービスです。
法人を設立する場合、本店所在地を記載する必要があります。
本店所在地を実際の仕事場である自宅にすると、プライバシーの問題が発生し、自宅住所を公表することに抵抗がある人はバーチャルオフィスを利用して、仮想のオフィスを住所とする事でプライバシーの問題を解決することが出来ます。
本題として、バーチャルオフィスを利用していると実際の仕事場か、仮想オフィスの住所のいずれにすれば良いか判断に悩む方が多いです。
バーチャルオフィスの場合、下記要素のどちらを重視すべきかを判断軸として本店所在地を決める事をおすすめします。
・利便性
・プライバシー
利便性を重視する場合、自宅を本店所在地としておくと、納税先が自宅から近い税務署となります。
ただし、自宅住所が容易に世間一般に公表されてしまいます。
一方でプライバシーを重視するのであれば、仮想オフィスの住所を本店所在地とする事で自宅住所を公表する必要がありません。
しかし、納税手続きなどが自宅近くの税務署にはならないため、利便性を考えると不利に働きます。
おすすめとしては、バーチャルオフィスの住所と自宅住所が同じ市区町村にして、本店所在地をバーチャルオフィスの住所にすれば、管轄税務署も自宅からそれほど遠くはならず、自宅住所を世間に公表する事も避ける事が出来ます。
◆税務調査時の注意点
バーチャルオフィスの法人に、税務調査が入った場合、下記2点について確認しておくことが重要になります。
・バーチャルオフィスに会議室はあるか
・バーチャルオフィスで必要書類の保管が可能か
バーチャルオフィスに会議室があれば、会議室で税務調査が可能ですが、会議室がない場合には自宅や別の場所を用意しておく必要があります。
また、税務調査は過去3年分を調査されるのが一般的です。
したがって、大量の書類を税務調査当日に持参するのは現実的ではありません。
バーチャルオフィス側で書類を保管してくれるかを事前に確認しておく事が重要になります。
◆まとめ
今回は、バーチャルオフィスを利用している法人の税務調査時における注意点を解説しました。
冒頭述べたように、リモートワークが普及した事によりバーチャルオフィスを利用している法人も増加しています。
バーチャルオフィスの法人が税務調査に入った場合には、会議室の有無や、書類の取り扱いについて事前に準備しておく事が重要になります。
今回の記事が、バーチャルオフィスを利用している事業者様の参考になれば幸いです。

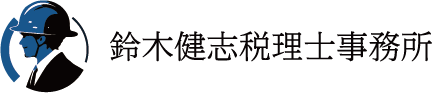 副業20万円ルールの正しい理解と実務対応
副業20万円ルールの正しい理解と実務対応